だらだら思いつくままに香港フィルのコンサートの感想を書いています
 カレンダー
カレンダー 
 リンク
リンク 
 フリーエリア
フリーエリア 
 最新CM
最新CM 
[10/26 ばってん]
[10/25 madame okami]
[06/07 ばってん]
[05/26 Kentaro]
 最新記事
最新記事 
(08/12)
(06/16)
(01/07)
(12/22)
(11/22)
(10/19)
(10/09)
(09/28)
(09/22)
(09/22)
 最新TB
最新TB 
 プロフィール
プロフィール 
 ブログ内検索
ブログ内検索 
 アーカイブ
アーカイブ 
 最古記事
最古記事 
(05/23)
(06/02)
(06/21)
(06/27)
(06/27)
(07/11)
(09/19)
(10/10)
(10/20)
(10/23)
 カウンター
カウンター 
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
メシアン; アセンシオン(キリストの昇天)
モーツアルト; レクイエム
指揮; マンフレッド・ホーネック
合唱; グルベンキアン合唱団
朗読; デヴィッド・タン
ソロイスト; Antoninette Halloran(S) Fiona Cambell(MS) Paul McMahon (T) Brian Montgomery (B)

通常聞かれるモーツァルトのレクイエムとは今回の演奏は全く異なっています(太字部分がモーツァルトのレクイエム)。
グレゴリオ聖歌
モーツァルトが父レオポルドに宛てた手紙(朗読)
グレゴリオ聖歌
フリーメイソンの葬送音楽 K.477
晩祷(ヴェスペレ) K.339
グレゴリオ聖歌
ネリーザックスの詩より(朗読)
第1曲:「入祭唱Introitus」
第2曲:「あわれみの賛歌Kyrie」
ヨハネの黙示録より6章8-17節(朗読)
第3曲:「続唱Sequentia」
Dies irae怒りの日
Tuba mirumラッパは不思議な音を
Rex tremendae恐ろしい王よ
Recordare思い起して下さい
Confutatis呪われた者は
Lacrimosa涙の日
ヨハネの黙示録より21章1-7節(朗読)
第4曲:「奉納唱Offertorium」
Domine Iesu Christe 主イエズス・キリストよ
Hostias et preces いけにえと祈りを
第3曲:「続唱Sequentia」よりLacrimosa涙の日(8小節のみ)
アヴェヴェルムコルプス K.618
(演奏されず)
第5曲:「感謝の賛歌Sanctus」
第6曲:「感謝の賛歌Benedictus」
第7曲:「平和の賛歌Agnus Dei」
第8曲:「拝領唱Communio」 「永遠の光Lux aeterna」
指揮者が登場すると厳かに鐘がなり、舞台裏からグレゴリオ聖歌が聞こえてくる。そして朗読やモーツアルトの別の作品が奏でられようやくレクイエムが。しかし全曲通して演奏されるのでは無く、聖書の朗読が入る。
朗読をしたデヴィッド・タンは上海灘や会員制レストランを手がけたビジネスマンなんですが、とても抑揚の効いた語りは、そこいらの俳優でもなかなか出来ないような巧さでした。音楽だけに没頭したいのに、なんて野暮な考えはこの演奏会を聴いた人にはおそらくいないはず。とにかく感動的でした。ひとえにモーツァルトの作品の凄さ。そしてこの日のプログラムの配置の巧みさ。フリーメーソンの葬送音楽をまず演奏、終わりはLacrimosaの断片のあとにをアヴェ・ヴェルム・コルプス。pppppな出だしで殆ど聞こえない位の音でオケと合唱が演奏を始める。もっともモーツァルトの音楽で美しい作品と言われているアヴェ・ヴェルム・コルプスで最後を締め、再び荘厳な鐘の音で演奏会は終了した。
このレクイエムの作品のバックグランドを知っている方には、Lacrimosaを最初の8小節だけで中断してしまうか、第5曲以降が演奏されなかったかお分かりでしょうね?モーツァルトはLacrimosaの最初の8小節までを遺して、この世を去ったのです。そして第5曲以降はジェスマイヤーが作曲されて完成されたもの(第4曲の「奉納唱Offertorium」は断片やスケッチを元にジェスマイヤー補筆されたらしい)。
見知らぬ男から依頼されたレクイエムの作曲、それが自らの鎮魂歌として作曲する心境におそらくモーツァルトはあったのと思います。そうでなければ、このような心の奥底をえぐり出すようなレクイエムをモーツァルトは作曲しなかったはず。死に対する不安と恐怖、本来心安らかに死者を弔う音楽を作曲するはずなのに、自分の心境を吐露しているような作品になってしまっています。ミューズの使いとして彼はこの世に現れてきたけど、モーツァルトも所詮はやはり生身の人間だったのだ、と、この作品を聴くと実感します。
CDで聴くレクイエム、作品の完成度からいくとムーティ&ベルリンフィルがダントツ。指揮者もソロもオケも合唱団もとんでもないほど素晴らしい出来映え。聞いた話ではムーティはこの録音に大変満足して「おそらく今後モツレクは録音しないだろう」と語ったとか。しかしぼくはやはりバーンスタインとバイエルン放響だな。この演奏は明らかに常軌を逸した演奏。レニーの亡き妻フェリシア・モンテアレグレ(このジャケットに載っている彼女)の没後10年追悼コンサートの録音がこれだから(DVDも出ています)。
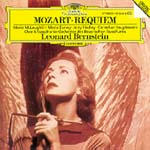
モーツアルト; レクイエム
指揮; マンフレッド・ホーネック
合唱; グルベンキアン合唱団
朗読; デヴィッド・タン
ソロイスト; Antoninette Halloran(S) Fiona Cambell(MS) Paul McMahon (T) Brian Montgomery (B)
通常聞かれるモーツァルトのレクイエムとは今回の演奏は全く異なっています(太字部分がモーツァルトのレクイエム)。
グレゴリオ聖歌
モーツァルトが父レオポルドに宛てた手紙(朗読)
グレゴリオ聖歌
フリーメイソンの葬送音楽 K.477
晩祷(ヴェスペレ) K.339
グレゴリオ聖歌
ネリーザックスの詩より(朗読)
第1曲:「入祭唱Introitus」
第2曲:「あわれみの賛歌Kyrie」
ヨハネの黙示録より6章8-17節(朗読)
第3曲:「続唱Sequentia」
Dies irae怒りの日
Tuba mirumラッパは不思議な音を
Rex tremendae恐ろしい王よ
Recordare思い起して下さい
Confutatis呪われた者は
Lacrimosa涙の日
ヨハネの黙示録より21章1-7節(朗読)
第4曲:「奉納唱Offertorium」
Domine Iesu Christe 主イエズス・キリストよ
Hostias et preces いけにえと祈りを
第3曲:「続唱Sequentia」よりLacrimosa涙の日(8小節のみ)
アヴェヴェルムコルプス K.618
(演奏されず)
第5曲:「感謝の賛歌Sanctus」
第6曲:「感謝の賛歌Benedictus」
第7曲:「平和の賛歌Agnus Dei」
第8曲:「拝領唱Communio」 「永遠の光Lux aeterna」
指揮者が登場すると厳かに鐘がなり、舞台裏からグレゴリオ聖歌が聞こえてくる。そして朗読やモーツアルトの別の作品が奏でられようやくレクイエムが。しかし全曲通して演奏されるのでは無く、聖書の朗読が入る。
朗読をしたデヴィッド・タンは上海灘や会員制レストランを手がけたビジネスマンなんですが、とても抑揚の効いた語りは、そこいらの俳優でもなかなか出来ないような巧さでした。音楽だけに没頭したいのに、なんて野暮な考えはこの演奏会を聴いた人にはおそらくいないはず。とにかく感動的でした。ひとえにモーツァルトの作品の凄さ。そしてこの日のプログラムの配置の巧みさ。フリーメーソンの葬送音楽をまず演奏、終わりはLacrimosaの断片のあとにをアヴェ・ヴェルム・コルプス。pppppな出だしで殆ど聞こえない位の音でオケと合唱が演奏を始める。もっともモーツァルトの音楽で美しい作品と言われているアヴェ・ヴェルム・コルプスで最後を締め、再び荘厳な鐘の音で演奏会は終了した。
このレクイエムの作品のバックグランドを知っている方には、Lacrimosaを最初の8小節だけで中断してしまうか、第5曲以降が演奏されなかったかお分かりでしょうね?モーツァルトはLacrimosaの最初の8小節までを遺して、この世を去ったのです。そして第5曲以降はジェスマイヤーが作曲されて完成されたもの(第4曲の「奉納唱Offertorium」は断片やスケッチを元にジェスマイヤー補筆されたらしい)。
見知らぬ男から依頼されたレクイエムの作曲、それが自らの鎮魂歌として作曲する心境におそらくモーツァルトはあったのと思います。そうでなければ、このような心の奥底をえぐり出すようなレクイエムをモーツァルトは作曲しなかったはず。死に対する不安と恐怖、本来心安らかに死者を弔う音楽を作曲するはずなのに、自分の心境を吐露しているような作品になってしまっています。ミューズの使いとして彼はこの世に現れてきたけど、モーツァルトも所詮はやはり生身の人間だったのだ、と、この作品を聴くと実感します。
CDで聴くレクイエム、作品の完成度からいくとムーティ&ベルリンフィルがダントツ。指揮者もソロもオケも合唱団もとんでもないほど素晴らしい出来映え。聞いた話ではムーティはこの録音に大変満足して「おそらく今後モツレクは録音しないだろう」と語ったとか。しかしぼくはやはりバーンスタインとバイエルン放響だな。この演奏は明らかに常軌を逸した演奏。レニーの亡き妻フェリシア・モンテアレグレ(このジャケットに載っている彼女)の没後10年追悼コンサートの録音がこれだから(DVDも出ています)。
PR
この記事にコメントする


